人材不足に悩む中小企業の経営者の皆さま、業務効率化の切り札をご存知ですか?
中国発の自律型AIエージェント「Manus」が自ら考え、判断し、行動する革新的なツールとして注目を集めています。
単なるチャットボットではなく「デジタル従業員」として機能するManusは、限られた人的リソースで多くの業務をこなす中小企業にとって理想的な解決策となるでしょう。
マーケティングから財務管理、顧客対応まで幅広い業務を自動化し、業務の属人化も防ぐことができます。
この記事では、Manusの機能と2つの月額制プランについて詳しくご紹介します。
- Manus AIの自律型エージェントとしての基本的な仕組み
- StarterとProの2つの月額制プランの違いと選び方
- マーケティングや財務管理、顧客対応の自動化機能
- スモールビジネスの人手不足や業務属人化の解決方法
Manus AIとは?中小企業に革命を起こす理由
Manus AIは自律的に考え、判断し、行動できる画期的なAIツールです。単なるチャットボットではなく、デジタル従業員として機能し、特に人材や専門知識が限られた中小企業の業務効率化を強力に支援します。
自律型AIエージェントの仕組みとは
Manusは通常のAIと異なり、ユーザーが目的を伝えるだけで自分で考え、判断し、一連の作業を自動的に実行します。例えば、新商品のアイデアを考えてほしいと依頼すると、市場調査から競合分析、アイデア提案まで一貫して行います。その核となる技術は以下の特徴を持っています。
- マルチエージェントアーキテクチャによる複数AIの連携
- 29種類のツール(ブラウザ、エディタなど)との連携機能
- クラウド上での動作によるバックグラウンド処理の継続

マルチエージェント構造により、Manusは複雑な作業も自律的に分割して処理できます。
技術的には「プランナー」「実行者」「検証者」などのサブエージェントが連携して動作し、大きなタスクを小さく分割して効率的に処理します。これにより、ユーザーは最初の指示だけで複雑な業務も完了させることが可能になりました。
中小企業がManus AIを導入するメリット
中小企業がManusを導入する最大の利点は、限られた人的リソースを最大限に活用できる点にあります。Manusは単なるツールではなく「デジタル従業員」として機能するため、経営者や従業員がより創造的で戦略的な業務に集中できる環境を作り出します。



専門チームを雇う余裕のない企業でも、専門家レベルのサポートを受けられます。
特に人材不足に悩む中小企業にとって、Manusがもたらす「専門知識の民主化」は大きな価値があります。データ分析や市場調査、法的文書作成などの専門分野で高度なサポートを提供し、意思決定の質とスピードを向上させます。
IT人材が少ない中小企業でもWebサイト構築やマーケティング資料作成を効率化できるため、限られた人材をより創造的な業務に振り向けることができるでしょう。
月額制プランの特徴と選び方
Manus AIは2025年3月に正式に月額制プランをリリースし、スモールビジネスの規模や利用目的に応じて選べる2つのプランを提供しています。適切なプラン選択で予算に見合った業務効率化が実現できます。
StarterとPro、2つのプランの違い
Manus Starterプランは月額39ドル(約6,000円)で提供され、月に3,900クレジットが付与されます。このプランでは2つのタスクを同時に実行でき、AIエージェントの活用を始めたばかりの個人事業主や小規模ビジネスに最適です。
一方、Manus Proプランは月額199ドル(約30,000円)で、月に19,000クレジットが付与され、最大5つのタスクを同時実行できます。



無料ユーザーにも1,000クレジットが付与されるため、まずは試してから検討できます。
両プランに共通する特徴として、専用リソースによる安定性向上、拡張されたコンテキスト長、混雑時の優先アクセスなどがあります。クレジット消費量は単純なタスクで150〜200、複雑なタスクで500〜600ほどなので、Starterプランでは月に約20回、Proプランでは30〜100回程度の利用が可能となっています。
自社に合った最適なプランの選び方
自社に最適なManusのプランを選ぶには、いくつかの重要な要素を検討する必要があります。まず利用頻度と必要な機能を明確にしましょう。日常的に多くのタスクを処理する必要があるか、あるいは高度なAIモデルの利用が不可欠かどうかで選択が変わってきます。
- 週に数回程度の利用ならStarterプランで十分
- データ分析や複雑なタスクが多い場合はProプランが効率的
- 複数人での利用ならタスク同時実行数の多いProプランを検討
予算とチーム規模も重要な判断基準です。月額いくらまで投資できるか、何人でManusを利用するかによって最適なプランは異なります。



具体的な業務内容によっても選択は変わります。市場調査程度ならStarter、Web制作ならProがおすすめです。
プラン選択の実践的なアプローチとしては、まず無料枠の1,000クレジットを使って実際の業務タスクをManusに依頼し、クレジット消費量と成果物の質を記録してみることをおすすめします。ビジネスの成長に合わせて段階的にアップグレードする柔軟性も持っておくとよいでしょう。
Manus AIの業務効率化機能とは?
Manus AIは従来のAIツールとは異なり、自律的に業務を遂行できるため、マーケティングから財務管理、顧客対応に至るまで幅広い業務プロセスを効率化します。特に人材不足に悩むスモールビジネスにとって心強い存在です。
マーケティングや財務管理の自動化
Manus AIはマーケティングと財務管理の分野で革新的な自動化を実現します。マーケティング分野では、戦略計画から実行、分析までを一貫して自律的に行います。市場調査やソーシャルメディアの傾向分析、競合他社の戦略把握など、人間のマーケターなら数日かかる作業も数時間で完了させることが可能です。
- コンテンツ作成と最適化の自動化
- ソーシャルメディア投稿のスケジューリングと分析
- 競合アカウントの活動モニタリング
これらの機能により、マーケティング担当者の負担を大幅に軽減できます。財務管理においても、データ収集から分析、レポート作成までを自動化します。



複数企業の株価データを収集し、相関分析を数分で完了させることも可能です。
財務レポートの分析や予算計画、キャッシュフロー管理など、専門知識を要する業務もAIが支援するため、専門スタッフがいない企業でも高度な財務管理が実現できます。
顧客対応や社内業務の時短効果
顧客対応や社内業務においてもManus AIは大きな時短効果をもたらします。Manusとチャットボットを連携させることで、顧客からの問い合わせに自動応答する体制を構築可能です。
これにより24時間365日の対応が実現し、オペレーターは複雑な問い合わせに集中できるようになります。



一部の企業では問い合わせ対応時間が従来の約70%削減されたという報告もあります。
社内業務においては、メールの送受信からスケジュール調整、データ処理まで多くの定型業務を自動化できます。議事録作成や音声の文字起こしなども効率化され、社員はより重要な業務に集中できるようになります。
また、データ処理の高速化も大きなメリットで、マルチエージェントによる並列処理でデータの収集・分析・レポート作成をリアルタイムで実行します。ヒューマンエラーの削減にも貢献し、手作業のミスを防ぎながら業務品質を向上させることができるのです。
モバイルアプリで場所を選ばず業務管理
2025年3月、Manus AIは待望のモバイルアプリをリリースし、スモールビジネスのオーナーや従業員が場所を選ばず業務を管理できる環境を整えました。外出先でも高度な業務処理が可能になっています。
スマートフォンで完結する業務処理
Manusのモバイルアプリの最大の特徴は、複雑な業務処理をスマートフォン一台で完結できる点です。従来のAIアシスタントアプリとは異なり、単に質問に答えるだけでなく、ユーザーの指示に基づいて自律的に行動し、タスクを完了させることができます。
例えば、外出先でも売上データの分析や資料作成を指示するだけで自動処理が可能です。
- 移動中や外出先での高度なデータ分析
- クライアント訪問中の即時資料作成
- 会議中のリアルタイムな情報収集と提案作成
このような機能により、特に外回りの多い営業担当者や複数の店舗を管理する経営者の業務効率が向上します。デスクトップ版と同様に2画面表示形式を採用しており、AIの思考プロセスと作業内容を同時に確認できる透明性も維持されています。



29種類のツールとの連携機能もモバイルで利用可能なため、PCと同等の処理能力を持ち歩けます。
リアルタイム通知で業務進行を見える化
Manusモバイルアプリの革新的な機能として、リアルタイム通知システムがあります。クラウド環境で動作するManusは、ユーザーがアプリを閉じていてもバックグラウンドでタスクを継続して実行し、重要なマイルストーンや完了時にプッシュ通知を送信します。これによりプロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握できます。



通知には優先度設定機能も備わっており、緊急性の高い情報は特別なアラートとして届きます。
例えば、大量のデータ分析を依頼した場合、「データ収集完了」「分析開始」「異常値検出」「レポート作成中」「タスク完了」といった各段階で通知が届くため、経営者や管理者は複数のプロジェクトを同時に監視できます。
チーム間のコラボレーションも強化され、マーケティング担当の調査結果が出たら製品開発チームに自動通知されるといった連携も可能になります。
これにより情報共有がスムーズになり、意思決定のスピードが向上するほか、パーソナライゼーション機能によりユーザーの行動パターンや好みに合わせた通知のカスタマイズも実現しています。
スモールビジネスが抱える課題とManus AIの解決策
日本のスモールビジネスは人手不足や業務の属人化などの課題に直面しています。Manus AIはこれらの問題を解決し、限られたリソースでも効率的な業務運営を可能にします。
人手不足をAIでどうカバーできるか
日本の中小企業の約7割以上が人手不足を実感しており、採用力や待遇面で大企業と比較して不利な状況にあります。背景には少子高齢化による労働人口の減少や、年功序列制度が残る中小企業では高いスキルを持つ人材が適正に評価されないといった問題があります。
- マーケティング業務の自動化と市場分析
- 財務管理における請求書処理やレポート作成
- 24時間365日の顧客対応体制構築
これらの機能により、人間のスタッフは創造的な業務に集中できるようになります。Manus AIは「デジタル従業員」として機能し、単なるツールではなく自ら考え判断する存在として働きます。



専門知識の民主化により、専門チームを雇えない企業でも高度な分析と意思決定が可能になります。
定型業務やルーチンワークの自動化効果も顕著で、議事録作成や音声の文字起こしなどの作業時間を大幅に削減できるのです。
業務の属人化を防ぎチーム全体で効率化
スモールビジネスが直面するもう一つの課題が「業務の属人化」です。少人数で事業を運営する企業では、特定の社員しか業務の詳細を把握していない状態が生じやすく、様々な問題を引き起こします。
属人化した業務は特定の社員しか処理できないため、その社員が不在の際にボトルネックが生じ、組織全体の効率が低下します。



属人化が進むと、マネージャーは業務の全体像を正確に把握できなくなり、適切な判断が困難になります。
Manus AIは業務の属人化を防ぎ、組織全体での効率化を実現します。例えば、AIを活用して業務の棚卸しを行い、業務内容と工数を可視化することで、最適な業務方法を社内ナレッジとして共有できます。
また、AIが業務マニュアルの整備を支援し、体裁がバラバラな既存のマニュアルを学習データとして読み込み、適切に整理・分類することも可能です。社内ヘルプデスクとしての機能も備え、学習したデータをもとに業務に関する質問に答えることで、特定の社員に頼らない情報共有を促進します。
まとめ
この記事では、中国発の自律型AIエージェント「Manus AI」の月額制プラン導入と、スモールビジネスの業務効率化について詳しく解説しました。
ポイントを簡潔にまとめると以下の通りです。
- Manus AIは自律的に考え、判断し、行動できる革新的なAIエージェント
- 月額39ドルのStarterプランと199ドルのProプランの2種類を提供
- マーケティング、財務管理、顧客対応など幅広い業務の効率化が可能
- モバイルアプリで場所を選ばず業務管理ができる
- 人手不足や業務の属人化といったスモールビジネスの課題を解決
Manus AIは従来のチャットボットとは異なり、ユーザーの指示に基づいて自律的に行動するデジタル従業員として機能します。
最適なプランを選ぶ際は、業務内容や利用頻度、予算を考慮することが重要です。無料ユーザーにも1,000クレジットが付与されるため、まずは試してから検討するとよいでしょう。
また、モバイルアプリとリアルタイム通知機能を活用することで、オフィスの内外を問わず業務の進行状況を常に把握し、効率的な業務運営が実現できます。
参照元:
- https://note.com/aieseshi/n/n4c2cd1eb59ef
- https://geekflare.com/news/manus-mobile-app-goes-live-with-claude-3-7/
- https://note.com/kyonkoizumi/n/n8025e392399c
- https://www.cryptotimes.io/2025/03/28/manus-ai-to-launch-its-mobile-app-for-its-users/
- https://weel.co.jp/media/innovator/manus/
- https://venturebeat.com/ai/what-you-need-to-know-about-manus-the-new-ai-agentic-system-from-china-hailed-as-a-second-deepseek-moment/

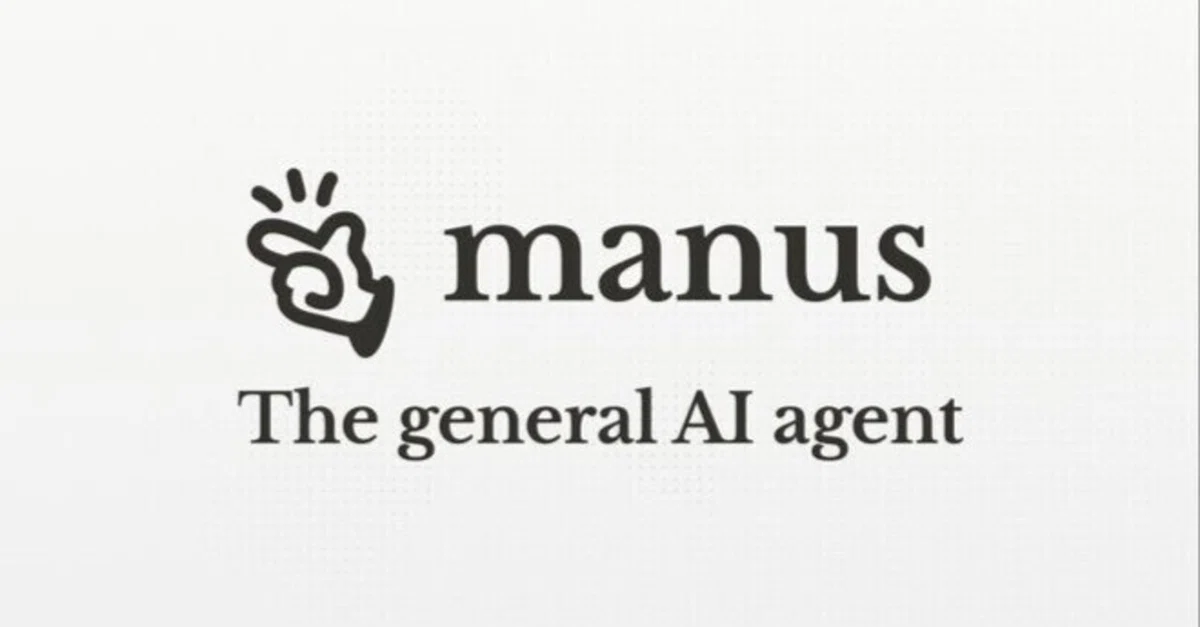
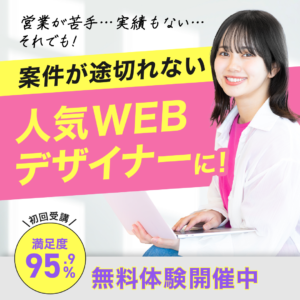
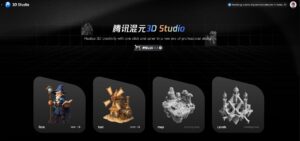
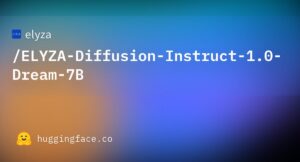






コメント